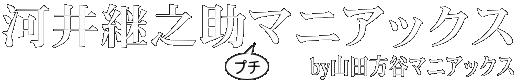
慶応3年10月、継之助の元に大政奉還の知らせが舞い込んだ。
長岡にいた継之助は、江戸へ急行。牧野忠恭・忠訓の二君に「天下の大勢は一変した。この時勢に長岡藩が傍観するだけでは、徳川氏に義理を欠き、王臣の道にも背く。牧野家は老中・所司代職も務めたのだから、上京して公武間の斡旋をしてはいかがか?」と進言した。
忠訓はこの進言を容れ、上洛することに決定、継之助ら六十余人を従え、幕艦順動丸に搭乗し大坂へ向かった。
上京した継之助は幕府と朝廷の間に入り、「徳川氏を弁護し、再び政権を復すことこそ道義でございます。」と説いた。この大胆かつ思い切った行動は、継之助本人にも先が見えない行動であり、大きなもめ事もなく朝廷に受理されたことを素直に喜んだと伝わっている。
上京に際し、継之助は当時の幕府筆頭老中であり、備中松山藩藩主である板倉勝静に継之助の見る今後の見通しを進言した。その内容は「戦うよりも一日も早く関東に引き上げ、まず内政を治め、時機を待とう、もし戦うとすれば京を守る兵はたかだか五千名。大津口・丹波口その他四辺の要路を絶てば、糧食窮乏してみずから潰れるはずです。」という物だった。しかし、会津、桑名の武将らの憤怒はすで頂点に達しており、この進言は受け入れられることはなかった。
そして、鳥羽伏見の戦い、大坂の玉津橋を警備していた継之助率いる長岡藩兵は慶喜らの遁走を聞く。「やはりか、まぁそれしかあるまいな。」
継之助の行動は意外と淡々としていた、継之助ら長岡藩一部対は大和路から伊勢に入り、松阪にでて海路、三州吉田を経て江戸に帰ることに。
藩主一行より先行して江戸に帰ってきた継之助は、意外に平穏な江戸の驚いたという、そして形勢を観望し、会津・桑名藩士と大槌屋で議論したり、藩邸の財産を処分し、兵器を買ったりした。
そもそも長岡藩にはこの当時流行していた攘夷思想があまりなかった。これは長岡藩に水戸学や国学の流れは少なく、六・七代藩主が賀茂真淵の門人となったほか、水戸学は筆頭家老の稲垣平助が影響されたが、いずれも少数で、幕末にはほとんど学ぶものもいなかった。藩学は実利を重んじたため実学を学ぶものが多く、洋学は流行のように藩士間に蔓延した。一方、藩主が海防掛老中職にあったため横浜などの異文化に触れるものが多く、懐夷思想は育たなかったからといわれる。
そんななか、継之助が打ち立てた思想とは「独立中立」という当時では考えられないような物だった。「我が藩は独り、その領地を守る」と主張した継之助は、時勢に任せず、藩の主体性を確立させようとした。継之助はこのとき「勤王佐幕の論外に立ち」と藩兵出兵の際に演説している。継之助率いる長岡藩は結果的には佐幕だったが、このころにはまだ完全な佐幕ではなかった。しかし薩長からしてみれば「独立中立」などは全く受け入れることのできる物ではなく、「長岡=佐幕」の公式が成り立っていた。
慶応四年初期、河井継之助はついに長岡藩の家老となり、筆頭家老稲垣平助は排斥されて兵学所取締の閑職となると、山本帯刀・牧野図書・稲垣主税の家老も継之助に従い、長岡藩は継之助の強固な支配体制を確立させていた。
そんな中、新政府軍の長岡藩に対ずる三万両の献金と出兵の命が下る、しかし継之助はこれを無視した。この時、継之助にどういう企図があったかは不明だが、小千谷会談の冒頭に、まず詫びている。
そして運命の小干谷談判、有名な会談であるが真相は謎にみちている。相手側の岩村精一郎は東山道軍の軍監であり、継之助も単身(二見虎三郎随行)で乗り込んだ。継之助は長岡藩の立場を述べるとともに、会津藩との間を調停してもよいと提案、しかし岩村は長岡藩の挙動を疑い、会津に与するものだと決めつけた。岩村が話し合おうとしない姿勢に、大村益次郎の遠略説があったというものもあるが、謎の多い会談といる。
何にしても継之助が思い描いていた理想はこのときに打ち砕かれた、若干24歳の軍監・岩村は継之助がいかに「独立中立」を説いても全くとりつく島さえなく、運命の会談は全くの破談となってしまった。これにより長岡藩の決起が決定図けられる、もしここで岩村でなく、ほかの人間であったならばその後の日本の未来も変わっていたという人間も多い。
小干谷談判決裂の翌々日の五月四日、長岡藩は越後五藩とともに奥羽越列藩同盟に加盟した。
慶応四年五月、遂に新政府軍は越後に進軍してきた。対して越後口に出兵する会津藩兵は、旧幕府脱走の衝鉾隊と合して、主力を小出島(北魚沼郡小出町)と小千谷(小千谷市)に置いた。
小千谷会談の翌朝、継之助は前島村にいた川島億次郎に昨日の様子を伝え、新政府軍の横暴を訴え、開戦もやむなしと同意を求めた。そののち、日頃、非戦をいう川島と同行して、摂田屋村の本陣に諸隊長を集めて開戦の演説をした。長岡軍は三個大隊の編成で、兵力はおよそ千三百余名。
継之助はこの戦争に勝つ自信があったといわれる。それは新政府軍側の薩摩・長州を中心にした兵力に限りがあること。戊辰戦争の展開が、同盟軍に有利になれば、新政府軍に参軍している各藩は同盟軍に同情的であるから、寝返る可能性があること。そのほか地の利の雪国の特性を生かせば、南国の兵は敗れるであろうと予測していた。
実際戦況は最初、同盟軍有利だった。戦術拠点としての朝日山の重要性を最初に着目した同盟軍は山頂を占守し、桑名藩士・立見鑑三郎を指揮者にして猛攻を撃退した。
しかし戦況は一気に変わる。長岡城下の西には大河信濃川が流れている。対岸には新政府軍が城下に向かって砲撃を開始していた。守る側は藩境に多数派兵しているので手薄であったが、折からの洪水に助けられていた。そこへ川霧を利用して新政府軍百名が強行渡河していっきに長岡城を落城させた。
落城の前日、信濃川畔を視察した継之助は、守衛する兵士に「二日間維持せよ」と伝達した。継之助は一個大隊半の兵を上流から渡河させ、一隊は小千谷本営、もう一隊は対岸の敵の背後にまわって攻撃するという作戦を企てていた。
長岡落城の知らせを聞いた長岡軍は 主力の半隊が救援に駆けつけた。長岡藩本陣にいた継之助はガトリング砲一門を従えて救援に向かい、城門でガトリング砲をみずから発射している。多くの兵士は城下で戦死することを望んだが、落城がはやく、果たせず加茂まで落ち延びた。
。
継之助は長岡城奪還を藩兵に説得し、より結束を固めさせ、藩兵を会津へ落ち延びさせず、加茂(加茂市)に転陣を決めた。そして「今町の戦い」、街道を進む軍が牽制軍となり、左右に展開した本隊と別働隊が新政府軍の弱点を衝き、敵の背後にでて包囲繊滅する戦術をとった。地の利を使い、わずかな兵でも大敵を倒すことのできる戦法であった。
慶応四年七月二四日、長岡城東に位置し、魔蛇が棲むと怖れられていた八町沖を、長岡藩兵の決死の兵たちが渡渉して長岡城の奪還を成功させた。世に言う「八丁沖渡河戦」である。六百九十余名の長岡藩兵は敵中に飛び込み、新政府軍を敗走させた、この戦闘の際、継之助は長岡城下新町口で左膝を鉄砲弾に撃ち抜かれた。激戦となっていた新町口に督戦に赴く途中ということであったが、戦傷のことは側近に箱口令をしいた。長岡藩兵の士気が衰えるのを怖れたためで、手当もさせなかったという。
奪取した長岡城は、継之助の陣頭指揮を得られないまま、反撃してきた新政府軍によって落城した。新政府軍の立ち直りのはやさは山県狂介参謀の手腕によるところが多い。乱軍となった新政府軍を妙見村付近でまとめあげ反撃に転じ、四日で再度、長岡城を落城させた。
再落城後、長岡藩兵とその家族は、会津へ洛ち延びることになった。阿賀川沿いを遡上する津川口が新政府軍にいち早く押さえられたので、八十里越が会津への唯一の通路となった八十里越は越後の下田から、会津の入叶津に抜ける一里が八里に相当するという険しい山道。継之助は特製の担架に乗せられ山中に一泊して越えた。自嘲の一句がある。
「八十里こしぬけ武士の越す峠」
継之助は越後の山野を振りかえり涙ぐんだという。
自身の死を悟った継之助は備中松山出身の商人に「先生の教えを守った」と山田方谷師に伝言乞頼み、藩主の弟鋭橘公をフランスヘ亡命させるよう手配し、己の身を人葬にすることを命じた。
慶応4年8月16日 殉す 享年42歳
Copyright(C) 2001 備中高梁観光案内所
