| 復刻趣意
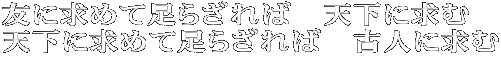
上は、山田方谷のもとに遊学した越後の河井継之助が、旅日記「塵壺」の備忘録に方谷の話として誌した一文である。
個人にむとは、古典に学ぶと解してもあながち間違いではなかろう。
今、私たちは、時代を切り拓く指針を、そして手法を、一人の古人に求めたい。
その古人とは、二百年前に生を受け、人の生きる道を尋ね、民の幸せを願い、辞せファイをになう人材の育成の実践躬行した山田方谷その人である。
昨今、山田方谷を扱う書籍は、小説はもとより財政改革の分析や思想の究明を主眼とする物まで多岐にわたって発行され、手軽に入手できる。だが、ここにも古典がある。一は明治四十三年に刊行された三島復の「哲人山田方谷」であり、一は昭和五年に出版された伊吹岩五郎の「山田方谷」である。
前者は報告の一番弟子ともいえる三島中洲の三男で陽明学の研究家としても名を馳せた著者だけに、父中洲から聞いた方谷にまつわるエピソードも実に多彩で臨場感に富み、しかも思想の解説も精緻を極める。一方、後者は、高梁の地で女子教育に生涯を捧げた著者が、教育界を退いた後に心血を注いだ書で、行間から方谷に対する敬慕の念と上梓に寄せる並々ならぬ熱意が伝わってくる。
惜しむらくは、両書とも古書店で目にすることも希で、また、所蔵する図書館も多くはない。また、随所に漢文・漢詩を引く旧体の文章は、現代人には決して読むのに容易ではない。だが、方谷の遺風がまだ色濃く漂う世に生を送った先人が、後世にその偉業を伝えんと精魂傾けた書物とつきあうことは、方谷に学ぶための有効なアプローチと考え、生誕二百年を機にここに復刻する。
復刻には福武文化振興財団から助成をいただいた。記して感謝申し上げる。
平成十七年六月
山田方谷顕彰会 |
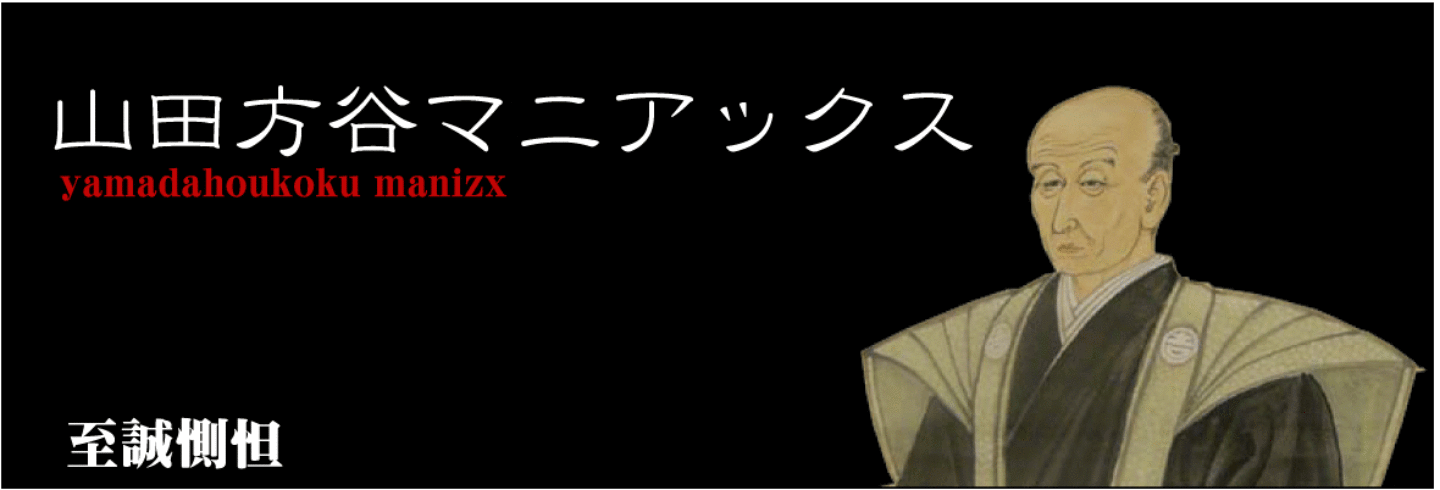
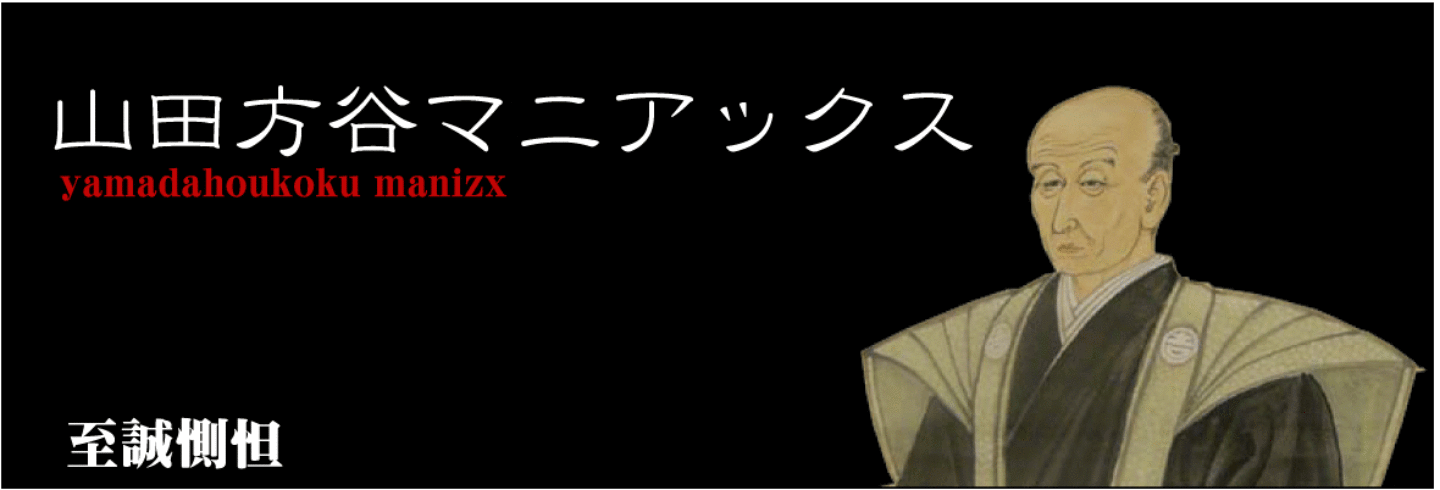
コメントを残す