「山田方谷と有終館」
高梁方谷会監査 児玉 享
山田方谷先生は五才より、新見の丸川松隠先生のもとで儒学・朱子学を学ばれ、のちには陽明学にも精通され、学者として、教育者として偉大な人生を歩まれた。
その学問的探求により得た学識と儒学の学習で得た人格と誠意のー心をもって、松山藩の政治の改革をされ、経済の再建をされた。孔子の目指した行き方、儒学は、自己の徳を高め仁の心をもって政治をおこない国を治め、人々の生活を平和で心豊かなものにするのを目ざす学問で、方谷先生が全力で追求していった学問である。
ここでは有終館の歴史を簡単に述べ、方谷先生と有終館、洋学との関係を見ながら、高梁図書館にある有終館蔵書を中心とする漢籍について概略述べてみたいと思っている。
漢学関係は良くわからないので不十分だと思いますがお許し下さい。また以後敬称は略します。
有終館について
松山藩が学問所を最初に開いたのは、板倉が入封して二年後の延享三(一七四六)年で、その場所は松山の本丁(現高梁市内山下御殿坂のほとり)であったが、以後五十年間は記録がないのでわからない。
藩校らしくなるのは四代藩主、板倉勝政の時代である。この頃、江戸幕府では松平定信(楽翁)の寛政の改革がおこなわれ、朱子学の官学化による政治理念の統一が図られた。そのため各藩はその意をうけて、藩校の設立による文武の奨励がなされた。板倉勝政の時に野村治右衛門(竹軒)は元締の職を辞して藩校の確立に務め、何より学問を好み読書好きな盧田利兵衛(北倶)を学頭に迎えて自らは助教として助けた。北漠は校名を下問され、「有終」と「日知」の二案を提出、勝政は「有終」を採用し、ここに藩校有終館が成立する。時に寛政十(一七九八)年と思われる。また水戸から松原某を迎え、儒臣として召し抱え、祭典釈菜の礼を定めた。
しかし、板倉勝政は学問に熱心ではなく、学問所の位置も定まらず、藩士も力を入れて学問しなかったようである。北漠のあと野村竹軒が学頭となったが、のち取締役にもどり、学問を好んだ奥田楽山が学頭に就任した。その後、藩が廃校を検討するところまでいったが、楽山は存続を強く建白しこれを阻止した。この点で楽山は有終館存続の功労者である。
有終館は天保二(一八三一)年に火災にあい焼失したが、中之丁に再建された。
天保七(一八三六)年、山田方谷が京都、,江戸での学習を認められ学頭となった。
天保十(一八三九)年の大火で焼失した後、彼は五年分の藩学の経費支出を願い再建している。
この有終館が盛んになったのは板倉勝静が七代藩主になり、藩士全員に有終館での学習を義務づけるなど、強く文武の修行を勧めてからである。
学頭は山田方谷のあと、進昌一郎(進鴻渓)、三島毅(中洲)が就任している。
中洲により文久元(一八六一)年学制改革が行われ、西洋学術の学習が導入されている。
明治維新後、板倉藩の存続が許されたが、すぐ廃藩置県で藩が廃止され、明治四(一八七一)年に有終館は閉校となつた。しかし、明治十二(一八七九)年に有志により再興され荘田霜渓が館長として多くの人材を送り出したが、明治二十(一八七九)年館長の死により終わる。
有終館の内容
板倉勝政の時代から整備されたと思われるが、中洲の時の改革でみると、
学習内容
文 一級 四書五経の素読
二級 四書講義
三級 五経講義
武 一級 初段
二級 目録
三級 免許
文武ともに一級が終われば殿様にお目見えが許され、二級を卒業すれば扶持米が与えられた。
指導者
学頭 一人
藩主の持講及び会頭の教導、年二度ほど殿中大広間にて全藩士に経典の講義をする
会頭 十人 句読師の教導
句読師 二十人 幼生の素読指導にあたる
文武目付 若干
板倉勝静以来藩士全員に有終館での学習が要求された。武士は六・七才になると有終館に通学し、文武ともに学習する。
「日本教育史」によると、幼生の素読は朝五ツ時より九ツ時まで句読師より個人指導をうけ、八ツより七ツまでは一人で復習する。
二級以上の講義生は朝五ツ時~昼八ツ時の間、教員の都合によって講義を受けるので、指導回数はだいたい一カ月当たり六~十二回となる。一方、教師である会頭・句読師も毎月三日と八日に朝五ツ時より学頭より経史類の講義を受ける。なお江戸時代の時刻は夜明け・日暮れともに六ツから始まり五ツ四ツ九ツ八ツ七ッとなつて一日を十二に分けている。季節によって夜明けなどの時刻が違っているが、ごくおおざっぱにいうと六ツは六時、一刻は二時間となる。したがって幼生の学習は午前八時から十二時、二時から四時の間となる。夏・冬で昼と夜の時間が違い、冬は夏より四~五時間夜の時間が長い。
方谷が冬の夜は勉学に適するので励むように言った理由がこれで理解できる。
また、有終館の中に寄宿舎を設けて優秀な子弟を入れて昼夜学習させ、更に優秀な者には文武ともに中央に留学させた。その学費は全て藩が負担している。
教本は四書五経、十三経、十八史略、日本外史、大日本史、二十二史、資治通鑑、宋元通鑑、諸子文集などである。
方谷と有終館
方谷が有終館で学び始めた後の学問研究を「山田方谷全集」の年譜よりの抜粋でみると、
方谷は文政八年二十一才の時特別に有終館で学ぶことを許され二人扶持(一日米一升)を給付された。これにより学資を得て文政十年二十三才のとき念願の京都遊学に出て寺島白鹿の門に学ぶ。その時、恩師丸川松隠より「斯文の淵源を探り求める」と儒学の道義の根源を探求してよく理解して郷里に帰ってくるように言われた。方谷はこれを真正面から受け止めて真剣に努力した。しかし短期間では探り得ず一旦帰国、二年後に再び京都に上り、師の宿題である儒学の道義の根源を追求する決心で白鹿の門に学ぶ。
この時、丸川松隠への便りで「天人合一の道理の自覚に達し、人間の道義の根源を自覚し、大賢君子の境地にのぼることに学問の目標を定めた」と書き送っている。
帰国すると中小姓格に上がり、有終館会頭になって八人扶持をもらう。しかし師の課題の答えを出したいと、今回は二年間の留学の許可をもらい、天保二年二十七才の時三度目の京都遊学に出る。彼は朱子学の学びだけでは答えが得られず、天保四年に伝習録を読んで陽明学を学び、誠意をもって実践努力をし良知を致すことにより終身の業に達すると理解した。
そこでさらに三年間の留学延期の許可を得て、江戸の佐藤一斎の塾に学び陽明学を深めている。都合五年間、儒学の根源の理解のため集中して学習している。
この執念と努力こそまさしく敬服に値し、方谷をすばらしい学識の深い人間に育てたと思う。一齋塾では佐久間象山と同居し、政治経済の改革の道について象山の洋学と方谷の儒学とで毎夜激論して相ゆずらなかった話がある。方谷もある程度洋学についての知識があったと思われ、のち西欧の学問技術を重視したのはこのあたりからかも知れないと思ったりしている。
天保七(一八三六)年十月有終館学頭を命じられ、御前丁に邸をもらい、学者らしい生活に入る。
天保九年より家塾を開き牛麓舎を称した。常に数十人が学び、進昌一郎も入塾、後塾長になる。三島毅が入塾するのは天保十四年であ
る。
牛麓舎の規模は、職業三条、立志、働行、遊藝である。
職業とは学問を終身の業として研究する意味かと思われ、また三条のうち遊藝とは論語に「道を志し、徳に拠り、仁に依り、藝に遊ぶ」とあり、藝とは詩文など教養のことで、高尚な詩文を楽しむ境地をいっていると思われる。
また禁遇六条として、学問を怠り、人を侮り自分はおごり、自分勝手に起きたり寝たり、飲食をし、おしゃべりをし、外出をすることを禁じ違反した場合一度は充分に忠告するが、再三犯す者は退塾願いを出して、即時退塾するよう厳しく行動をいましめて、勉学に専念することを求めている。
遊学に出る熟生には、その人に合った課題を与えている。学問について記すと、天保十四(一八四三)年、石川伯介が江戸に遊学に出た時の学習について、四書は一-種ごと繰り返し塾読、資治通鑑綱目を早々に一覧、唐宋八家文を常に塾読し、其の内二・三十篇は暗諦する。作文は一月に四・五篇は作るべし、とある。
又、養子耕蔵(弟の子供)の昌平校の修学心得は、経伝は学校の書研究、外に易、論語を細読、明清史を通読する。
文集・語録等はこちらで得難い大家の書を択んで読み、詩集は唐第一、宋は蘇・陸等の書を塾読、詩文を作るのは学校の題に従い、怠けないこと。
そのひとの学力に応じて具体的に指導し、自分が遊学中学習したように、ゆるみなく全力で学ぶことを要求している。
西洋学術について
方谷は清朝が一八四一年アヘン戦争に破れたことなど、情報を早く知り、西洋の軍事力洋式兵制に早くより関心を持つようになり、弘化四(一八四七)年洋式武器、銃陣など学ぶために、当時中国地方で最も進んでいた津山藩に中洲を伴って学習に行き、一月余り滞在して大砲の製造法、銃陣なども学び、庭瀬藩家老渡辺信義にも学び、二年後再び津山に行くなど洋式軍備を研究して、大砲を製造して試射している。
銃陣には、士族が銃の使用を好まなかったので嘉永五(一八五二)年に郡奉行を兼任したのを機に農兵を組織して訓練した。
安政五(一八五八)年の項に、「先生頗る西洋戦術を講究す。家に西洋戦図十六葉(一葉は美濃紙半分大・彩色)あり、瑞西独立戦、普填・普仏戦争等に属す」とあるが、普埋(一八六六)普仏(一八七〇)は時代が下がるのでナポレオン戦争時のものかと思われる。
その図をもとに農民兵を桔梗原で訓練し、それを見た長州の久坂玄瑞を驚かしている。
文久元(一八六一)年、三島毅は献策して、学頭に任じられ、有終館学制を革新した。要旨は、孔孟の道義に基づき、西洋の学術を合せ学ぶとあり、講経の間に「西洋事情」、「西洋立志編」、「自由の理」、「気海観瀾」など洋書の和訳を講義して西洋文物の知識を与え、更に学びたい有志の者は勧めて洋学修行のために江戸に出した。併し洋学の学習は停滞したようで、慶鷹三(一八六七)年に熊田恰に「洋学は備前藩などは洋学所お取立にて、我藩が西洋の事一番早く始めたのに大後れ……」と残念がっており、翌月には洋制を参考に文武の諸制を改革し、三島毅が洋学総裁を兼務している。
この洋学がどの程度有終館で学ばれたかを、書物を通して知りたいと思い、図書館の書庫に調べに入ったのが、私の書庫整理のきっかけである。
洋学の存在する書物を紹介しておくと、語学は早くは、幕府公認のオランダ語の辞典類「和蘭文典」
(四冊一八四二・四八年)「増補改正訳鍵」(一八五七)「洋学須知」
(二冊一八六六)ついで幕府のフランス兵制の導入と関連してか「仏語明要」(四冊一八六一)が、ついで英語リーダーの「英吉利初学初編」(一八六六)がある。
地図は嘉永二(一八四九)年刊の萬国地図の全図、一枚は東西半球図になっている。地歴では「八紘通誌」(一八五一年ヨーロッパ地誌)幕末頃の「泰西史鑑」(三冊)「地球説略」(八冊)「海国図志」(インドのみ一八五六年)があり、当時の世界各地域の地誌、歴史が知られる。
兵学は山田文庫に「鉄砲茶話」(五冊)の写があるが、有終館ではフランス兵法論の「慕氏兵論」(六冊一八六三年)が早い方で「兵家須知戦術部門」「仏蘭西答屈智機」(一八六七)と幕府がフランスの支援で軍事力の改革をはかっていると同じ傾向がみられ、ナポレオン以来のフランスの軍事論、行軍布陣等が紹介されている。
ただ方谷が}八五〇年代には、農兵制と西洋銃陣を確立したと思われるのに比べ、時代が下がるので紛失した本が多いのではないかと思われる。法律、経済面の本もあるが明治維新以後である。また山田文庫には「英国史」が大小十五冊(一八五六~六一)や「自由の理」などがある。進文庫には、十九世紀の中国を書いた「隣草」がある。
有終館その他文庫の蔵書について
高梁図書館の書庫に入ってみると、古い漢籍、国書など有終館の蔵書と山田、進、桜井など各文庫図書が約八千冊と、高梁高校の寄託図書を入れると、約】万冊近い本が整理されずに置かれていたので、まず整理に取りかかり、在庫の書名を書き出し、その整理方法について訪ね歩くうちに、東京で内閣文庫の長澤孝三氏に幸運にもお会いでき、全面的に指導してもらってやっと整理ができた。
現在書庫内に、有終館と各文庫とその他に分け、分類に応じて配置し、書名一覧を作っている。目録作りは私の手におえないので長澤氏にお願いしている。
現段階で書庫内の整理と書名一覧表をもとに漢籍の概略をお知らせする。
書庫内の蔵書について確認冊数を見ると
| 所属 | 総計数 | 漢籍数(含準漢) | 国書数 | その他 |
| 有終館 | 4,379 | 3,947 | 432 | |
| 山田文庫 | 879 | 598 | 281 | |
| 進文庫 | 782 | 658 | 124 | |
| 桜井文庫 | 1,861 | 1,472 | 197 | 192 |
| 中村他 | 189 | 148 | 41 | |
| 計 | 8,090 | 6,823 | 1,075 | |
| 高校寄託 | 1,847 | 699 | 1,148 | |
| 総計 | 9,937 | 7,522 | 2,223 |
以上高校寄託を含めても漢籍(漢文で書かれた書籍)が四分の三を占めている。有終館蔵書は、藩士の学習に役立つ漢籍が主で、五経・四書を初めとする儒学関係、史書、文学書が多く見られ、山田文庫は五経・四書の他に伝習録など陽明学関係の本と漢学者の著書など漢学学習の書が多く、進文庫は進鴻渓が川面で塾を開いた関係か、五経は十五秩(厚紙のカバーでまとめた)九五冊、四書は一二秩二五冊がまとまってあり、唐宋八大家文など文学書も多い。桜井文庫には史記から明までの二十二史三九九冊と、子書百家七六冊まとまってあり、文学、教養面の書が多い。
他に明治以後の法律書、英書がまとまって寄贈されている。
有終館蔵書の八割以上を占める漢籍を少しくわしく紹介すると有終館の蔵書は、生徒の学習用に備えられた書物と思われる。
古典である五経・儒学の聖典四書が多いが、歴史、文学も重視された様子がうかがえる。
五経は四九部六六二冊で易経類(陰陽の消長に宇宙の原理・万物の変化を見る、自然と人間の道理の解明)易学正義、易学大全など六九冊
書経類(中国最古の史書、春秋時代まで)
尚書註疏、書経大全など五三冊
詩経類(股~春秋の詩三一一冊)
毛詩正義、御纂詩義折中など五三冊
春秋類(魯の国を中心とする歴史書)
左博、春秋五博など一九六冊橿記類(礼に関する雑記、王室の制度、日常の礼儀など)周礼正義、礼記大全など二九五冊
(中国の時代、股1周1春秋1戦国1秦1宋1元1明1清)
四書十六部一五二冊大学・中庸はそれぞれ五経の礼記の一部を取出し、大学は儒学の入門書で根本原理を説明、そこでは心を正し、身を修め、家をととのえ、治国平天下がめざされ、九才の方谷が目標として答えたもので、松山藩で実現した。
「中庸」は中庸(中道)の徳は言葉通であるが高貴な本性「誠」により完成されると説く。「論語」は孔子と子弟の言行録で、「孟子」は孟子の問答を門人が編集したもの。
以上四書が、南宋の時代朱喜…が特に学ぶべき儒学の聖典として定めたもので、儒学の本流朱子学として日本でも中心として学ばれた。
陽明学に関連した伝習録、王陽明全集などあるが参考程度で方谷の方針で、まず朱子学による学習が行われていた。史部(歴史書)六十部五七七冊方谷は歴史の学習を重視し、特に各時代の制度の学習を望んだといわれる。
正史が揃っている、正史として史記以来明朝まで各王朝時代の歴史を紀伝体で書いている。
冊数が多いのは資治通鑑に関するもので、北宋の司馬光が周以後を編年体(年次的に各王朝時代の歴史を書いた)で書いたもの、津藩が天保七年出版したものを六箱(一箱一四八冊内三箱は一部紛失)購入している。
資治通鑑綱目は、資治通鑑を南宋の朱黒と弟子が選び要点を書いた綱と言葉をくわしく説明した目を五九巻一〇五冊にまとめたもので、江戸期の学者必読の書で一箱にまとまって入っている。
また、歴史綱鑑補二十冊(通鑑に関する諸書を合併しお互いに相綴じる)など、歴史を重視したことがうかがえる。
子部は二三部二六一冊
諸子百家に入る書物で、儒家の作品が多く朱子の近思録備考四冊、性理大全四八冊、他に小学書(朱子の弟子選)などあり、管子に関する四部十九冊、韓非子職原抄(全書)五六冊などがみられる。
集部など一一四七冊
集部の文学書も多く柳文(柳宗元)五二冊、韓文(韓愈)四七冊、文選正文六五冊他文選類六四冊、増評唐宋八大家読本十四冊、朱子文集(三十五冊)、淵鑑類亟(唐宋元明の詩文事績をあつめて整理、故事の検索に最良)十九秩一八八冊
集以外でも、武備志(一箱八一冊武備・兵事の歴史の事実論説を編輯)など多方面にわたっている。
併し、日本教育史(文部省明治二三年刊)の資料によると、経類(四書五経)一一五部(在六六)、史類一四二部(在六十)、子類二四三部(在二三)、集類六六部とあり、かなりの部数が失われている。
又、かなりの書物が他の文庫に移っているのかもしれない。
国書については、日本教育史には、日本外史、大日本史の書名があり、漢学を主として傍ら国書を読ましめ……とあるので、自ら学ぶ教材として、色々な分野の国書が用意されていたと思われる。頼山陽著の「日本外史」(文政十年刊、源平二氏から徳川氏の武家政権の盛衰、尊王思想)が二種三二冊、山田文庫に一二冊、進文庫二一冊がみられるが大日本史は見当らなかった。他に「古事記伝」、「萬葉集略解」などの日本古典や、「天文図解」など天文に関するものや、海防に関する林子平の「海図兵談」(九冊)や、学者などの説を集めた「海防彙義」など、多方面にわたり、幕末時の時代を知る書物も多い。
また、国学についても国学者として有名な平田篤胤は、江戸詰の藩士の養子になり一時松山藩士であったので「古史徴」など幾つかの書物が残っている。
以上、有終館蔵書について一部紹介したが、各文庫も含めて幕末時の方谷を中心として多くの学問研究がなされ、方谷は豊かな学識と学研的な学習で藩財政の確立だけでなく、全国的情勢や世界の動きも軍事技術も含めてかなり的確に把握して、藩政を指導していったと思われ維新時の藩の対応も的確になされている。
当時の松山藩の学問水準は高く、備中地区の中心として発展し明治維新以後多くの人材を中央に送りだしていった。
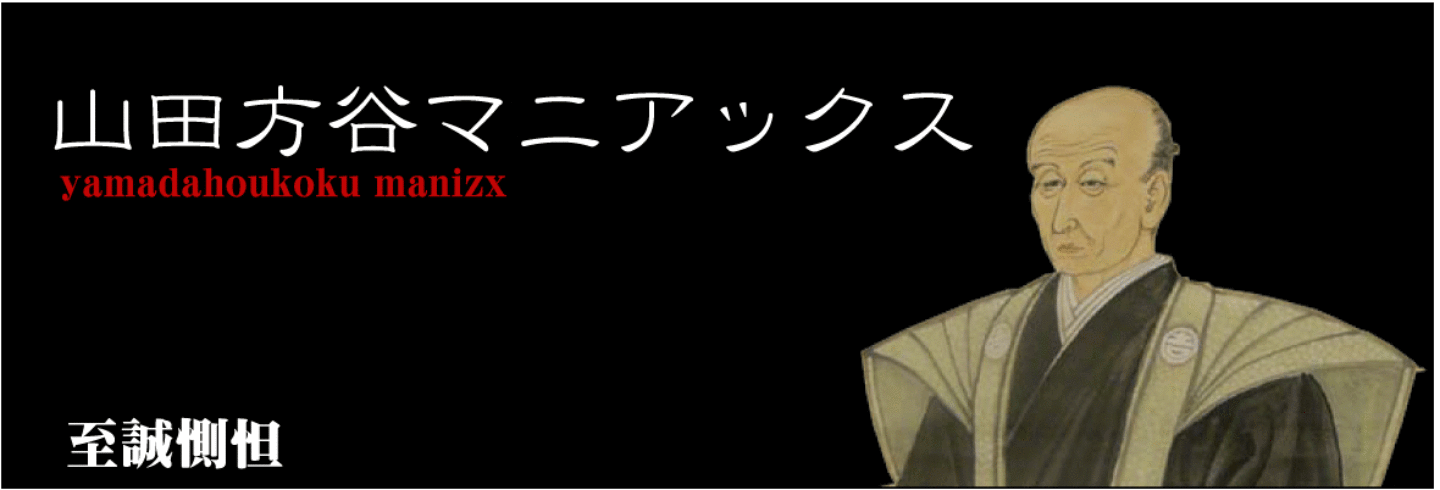
コメントを残す